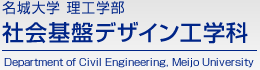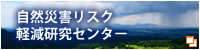防災・減災
コンピュータシミュレーションと実験を融合したサブストラクチャー実験システムの開発
コンピュータシミュレーションと構造実験装置を融合したハイブリッド実験システムを研究開発。そのシステムを応用して長大橋梁等の耐震性の向上に必要な制震デバイスの性能を高精度に検証する研究を行っています。
 サブストラクチャー実験システムの開発状況
サブストラクチャー実験システムの開発状況
 1軸制御サブストラクチャー実験システム構成の例
1軸制御サブストラクチャー実験システム構成の例
橋梁構造物の巨大地震時破壊挙動の数値シミュレーション
鋼製橋脚などの土木鋼構造物を中心に、地震などの過大な外力を受けた場合に構造物がどのような破壊モードを呈するのかを数値シミュレーションにより解明。極低サイクル疲労によるクラックなどに起因する構造物の損傷を精確に評価する方法の開発を進めています。
 極低サイクル疲労によるクラック
極低サイクル疲労によるクラック
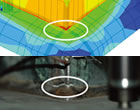 数値解析シミュレーション解析と実験による極低サイクル疲労現象の解明と予測
数値解析シミュレーション解析と実験による極低サイクル疲労現象の解明と予測
海溝型巨大地震時の地盤挙動の予測
地震時の自然地盤の力学特性を精密に得るための室内試験法を開発・実施。その結果をもとに自然地盤の動きを予測するモデルを構築し、海溝型巨大地震が実際に発生した場合を想定した地震時地盤挙動予測のシミュレーション解析を行っています。
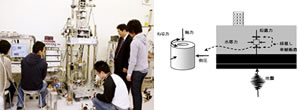 動的中空ねじりせん断試験による粘土地盤の地震時挙動の評価
動的中空ねじりせん断試験による粘土地盤の地震時挙動の評価
越流破堤現象の解明と減災対策の検討
近年多発している“豪雨災害”を受け、超過外力(豪雨)に対する減災対策が必要になっています。そのため、特に堤防の決壊現象に着目し、数値解析と実験を用いてきっかけによる破堤現象の進行過程の違いなどを検討し、進行を抑える対策について研究しています。
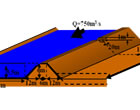 破堤する堤防と河川の条件設定
破堤する堤防と河川の条件設定
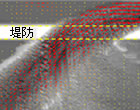 堤防破堤後の状況(平面河床コンターとベクトル図)
堤防破堤後の状況(平面河床コンターとベクトル図)
転波列性土石流サージの生成機構およびそのサージ波動特性に関する研究
土石流は、先端に大きな水深を有し、一つの塊のようなかたちで流れる現象として知られています。間欠的に多数の土石流が発生する機構(メカニズム)と、その流れるときの波状の高さや周期などの特性を明らかにする研究を行っています。
 中国の粘性土石流の例(写真手前と奥部に土石流の先端がある
中国の粘性土石流の例(写真手前と奥部に土石流の先端がある
 長さ56m水路での転波列性土砂流サージ実験
長さ56m水路での転波列性土砂流サージ実験
豪雨ならびに地震時の人工斜面の安全性評価手法の開発
近年頻発しているゲリラ豪雨などによって、河川堤防の決壊が後を絶ちません。また、東日本大震災でも数多くの河川堤防が被災しましたが、東海地方でも南海トラフ地震の発生が懸念されています。洪水や地震による自然災害を防いだり、軽減したりするために、河川堤防の合理的な安定性評価手法の開発を進めています。
 堤防で採取した砂礫の力学特性を調べる室内試験
堤防で採取した砂礫の力学特性を調べる室内試験
 台風による豪雨で破堤した河川堤防と堤防の浸透破壊解析例
台風による豪雨で破堤した河川堤防と堤防の浸透破壊解析例
橋梁の制震化に必要な制震ブレース接合部の最適化に関する研究
橋梁の制震化に適用される制震デバイス(例えば座屈拘束ブレースなど)を橋梁主構造と接合するガセット接合部の、最適な設計法を確立するための実験及び解析的研究を行っています。
 ガセット接合部の性能検証実験の様子
ガセット接合部の性能検証実験の様子
津波襲来時大型漂流物の長大橋衝突シミュレーション
東日本大震災では大規模な津波が発生し、広い範囲の構造物に対して壊滅的な被害をもたらしました。津波が直接的な原因と考えられる被害の他に、津波が船舶やコンテナを押し流し、漂流物となって構造物を損傷・破壊した二次的な被害も甚大でした。こういった、偶発作用における挙動や構造物への被害を、数値シミュレーションによって明らかにする手法の開発を進めています。
 津波発生時の大型船舶と橋梁の衝突
津波発生時の大型船舶と橋梁の衝突
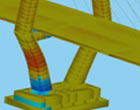 衝突後の主塔基部損傷状況
衝突後の主塔基部損傷状況